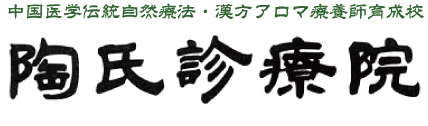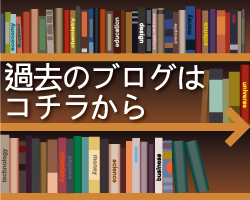2025-05-24
入郷随俗(郷に入っては郷に従え)
2025-05-23
養生の陰と陽
2025-05-22
ラ・ブレア・ター・ピッツ & 博物館の衝撃
2025-05-21
同級生との命についての熱い議論
2025-05-20
CPP卒業式に参加して
2025-05-19
反ユダヤ主義の残響とポグロムの影響展を訪れて
2025-05-18
アメリカ旅行三日目
2025-05-17
AI依存と自立の教育問題
2025-05-16
アメリカ旅行二日目
2025-05-15
アメリカ初日
2025-05-14
五官からの健康チェック
2025-05-13
中国医学では、なぜ痔の治療を頭の「百会」で行うのでしょうか?
2025-05-12
形の美しさと音の響きを重視した漢字の活用
2025-05-11
家族診療の日の記録更新
2025-05-10
医学における「道」と「術」
過去ブログはこちらから
4
入郷随俗(郷に入っては郷に従え)
中国のことわざ「入郷随俗(郷に入っては郷に従え)」は、新しい土地に住んだり、環境が変わったりしたときには、その地の風習や慣習に順応し、従うことが大切だという教えです。
先日、アメリカで同級生に会いました。東洋文化とは異なる西洋文化を理解し、適応することは、現地社会に溶け込むうえで非常に重要だと実感しました。教科書には載っていない常識を知っていることが、職場でのトラブルを防ぐためにも役立ちます。まさに、「郷に入っては郷に従え」の精神です。
同級生の奥様は、アメリカの大手石油会社で海外担当として勤務しており、東南アジアへの出張も多いそうです。ある時、仕事でのメールのやり取りの中で、日本側の貿易担当者から、彼女の名前の後に書かれていた「SAN(さん)」について、「これはどういう意味ですか?」と尋ねられたことがあったそうです。
私の理解では、「さん」は日本語における敬称の一つで、性別に関係なく相手に対して敬意を表すときに使われます。
次に出た質問は、「相手の名前を呼ぶときに、苗字と名前のどちらを使うべきか」というものでした。中国や日本など東洋の文化では、通常、苗字を呼びます。これは、西洋と東洋で名前の書き方の順序が異なることに関係しています。
西洋の英語圏では、氏名の順番は「名(ファーストネーム)→ ミドルネーム → 姓(ラストネーム)」です。ファーストネームは、本人に与えられた固有の名前であり、通常、日常会話ではこの名前で呼び合います。これは、個人を重視する文化が背景にあります。
一方、東洋では「姓 → 名」という順番です。英語表記とは逆になります。そのため、家族や集団を重視する東洋文化では、苗字で呼ぶことが一般的です。特に中国では、姓は一文字がほとんどで、苗字が分かりやすい特徴があります。
しかし、日本人の氏名(たとえば四文字のフルネーム)は、英語話者や同級生の句さんのような日本語を分からない方から見ると、どちらが姓でどちらが名か判別しづらいこともあるようです。
海外旅行の際、入国カードに記入する時など、こうした文化的な違いを理解していれば、誤解や記入ミスも少なくなるでしょう。
先日、アメリカで同級生に会いました。東洋文化とは異なる西洋文化を理解し、適応することは、現地社会に溶け込むうえで非常に重要だと実感しました。教科書には載っていない常識を知っていることが、職場でのトラブルを防ぐためにも役立ちます。まさに、「郷に入っては郷に従え」の精神です。
同級生の奥様は、アメリカの大手石油会社で海外担当として勤務しており、東南アジアへの出張も多いそうです。ある時、仕事でのメールのやり取りの中で、日本側の貿易担当者から、彼女の名前の後に書かれていた「SAN(さん)」について、「これはどういう意味ですか?」と尋ねられたことがあったそうです。
私の理解では、「さん」は日本語における敬称の一つで、性別に関係なく相手に対して敬意を表すときに使われます。
次に出た質問は、「相手の名前を呼ぶときに、苗字と名前のどちらを使うべきか」というものでした。中国や日本など東洋の文化では、通常、苗字を呼びます。これは、西洋と東洋で名前の書き方の順序が異なることに関係しています。
西洋の英語圏では、氏名の順番は「名(ファーストネーム)→ ミドルネーム → 姓(ラストネーム)」です。ファーストネームは、本人に与えられた固有の名前であり、通常、日常会話ではこの名前で呼び合います。これは、個人を重視する文化が背景にあります。
一方、東洋では「姓 → 名」という順番です。英語表記とは逆になります。そのため、家族や集団を重視する東洋文化では、苗字で呼ぶことが一般的です。特に中国では、姓は一文字がほとんどで、苗字が分かりやすい特徴があります。
しかし、日本人の氏名(たとえば四文字のフルネーム)は、英語話者や同級生の句さんのような日本語を分からない方から見ると、どちらが姓でどちらが名か判別しづらいこともあるようです。
海外旅行の際、入国カードに記入する時など、こうした文化的な違いを理解していれば、誤解や記入ミスも少なくなるでしょう。
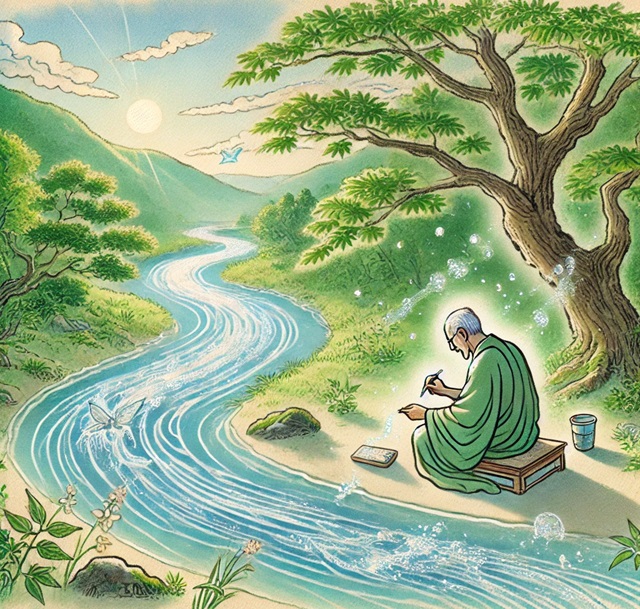
2025-05-24