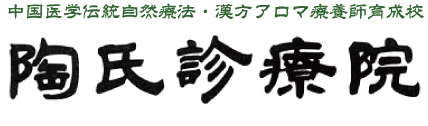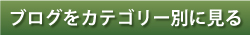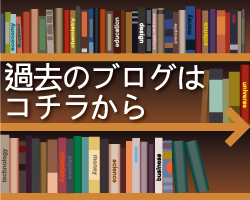▼日本バックナンバー
2025-10-19
枯損率20%から0.3%へ ― FFCが海岸防災林復興に貢献!
2025-10-18
70代の訃報
2025-10-13
今年最後のパークゴルフ
2025-10-05
先輩たちの成功体験に学ぶ~教育と人生の可能性を語り合う会
2025-09-30
学校法人藤天使学園 創立100周年記念式典
2025-09-21
北海道大学散策とクジラについての学び
2025-09-16
日本の100歳以上人口、過去最多の9万9763人に ~55年連続増加~
2025-09-15
朝ドラが好きな理由
2025-09-07
日本国内報道の違和感
2025-09-03
宰相と首相
2025-09-02
昭和の衝動
2025-09-01
町内会のパークゴルフ
2025-08-31
共に創る「教育」の未来
2025-08-30
9月3日中国「抗日戦争勝利80年」軍事パレード参加外国首脳名簿発表
2025-08-28
敬老の日の祝い配布について
過去ブログはこちらから
昭和の衝動
カテゴリー 日本
映像の世紀バタフライエフェクト シリーズ昭和百年(1) 戦時下の宰相たち
冒頭に紹介された陸軍大臣の演説「内地満州相携えて、まず東洋の平和を確立」この言葉から番組は始まります。
昭和初期、日本は不況に苦しんでいました。その状況を打破したのは、皮肉にも戦争がもたらした経済復興でした。満州国建国により軍需産業と輸出が拡大し、失業率も改善。国民は「戦争がもたらす好景気」を実感し、中国との戦争を歓迎、さらにアメリカとの戦争を望む空気すら生まれていきます。
満州事変と宰相たち
1931年9月18日、奉天(現在の瀋陽)郊外で南満州鉄道の線路が爆破されました(柳条湖事件)。これをきっかけに関東軍は独断で軍事行動を展開し、満州全土を占領。最終的に傀儡国家「満洲国」を樹立します。番組では、この爆破が関東軍の自作自演であったことを認めています。
当時の第28代首相・若槻禮次郎は、政府方針に反する軍の独断行動を追認せざるを得ませんでした。満州国を宣伝する映画では、こう語られます。「満蒙の天地はまさに我々日本人によって開発されねばなりません。このまま推移すれば、日本国民はただ座して死を待つのみです。総額130万平方キロの豊かな資源に恵まれた満蒙を開拓することによってこそ、日本は国防的にも経済的にも存立しうるのです。」
大阪朝日新聞は、爆弾事故で亡くなった3名の軍人を「軍神・肉弾三勇士」と讃え、虚偽の記事を国民に広めました。映画や歌まで制作され、国民の戦意は高揚していきました。
犬養毅と軍部台頭
満州国に反対した第29代首相・犬養毅は1931年12月に就任しましたが、1932年5月15日、五・一五事件で暗殺されます。後を継いだ第30代首相・斎藤實(海軍大将)のもとで政党内閣は終焉を迎えました。
1936年の二・二六事件では、陸軍青年将校らが政府要人を襲撃し、永田町・霞が関一帯を占拠。軍を批判した東京朝日新聞も標的となり、新聞は軍を自由に批判できなくなりました。しかし昭和天皇の強い怒りによって鎮圧され、青年将校たちは投降、あるいは自決して事件は収束します。この結果、岡田内閣が総辞職し、後継の広田内閣は思想犯保護観察法を成立させました。
近衛文麿の登場
首相推薦の重責を担った元老・西園寺公望は、軍の暴走を抑えるため近衛文麿を首相に選びます。第1次近衛内閣では、盧溝橋事件をきっかけに日中戦争が勃発。近衛は不拡大方針を掲げましたが軍の強硬論に押され、「北支派兵声明」「近衛声明」「東亜新秩序」などを打ち出し、国家総動員法を施行して戦時体制を強化しました。
その後も新体制運動を唱え大政翼賛会を設立し、国内の全体主義化を推進。外交面では「八紘一宇」「大東亜共栄圏」を掲げ、日独伊三国同盟や日ソ中立条約を締結しました。戦後は東久邇宮内閣の国務大臣として憲法改正に意欲を見せましたが、A級戦犯に指定され、服毒自決しました。
戦争と国民
戦時下の新聞は連日勇ましい記事で国民を煽り、批判はほとんど不可能でした。近衛文麿は外交で対米戦争を避けようと努力しましたが挫折。後継の東条英機も交渉を続けましたが、国民世論の熱狂を抑えきれず、最終的に開戦を決断します。
南京陥落後、国民は領土拡大や賠償金に大きな期待を抱きました。ちなみに、日清戦争後の下関条約で清国から得た賠償金(計2億3,150万両、庫平銀)は、当時の日本GDPの約4割に相当しました。この成功体験が、国民にさらなる戦果を期待させていきます。
戦争が長引くにつれ、中国を支援する英米との対立が深まり、日本はドイツ・イタリアと軍事同盟を結び、やがて世界規模の戦争へ突入していきました。
映像を通じて、私たちは「なぜ日本が第二次世界大戦に参加していったのか」、その歴史的背景の一端を理解できます。歴史を知らない若い世代こそ、この番組を見るべきだと思います。
冒頭に紹介された陸軍大臣の演説「内地満州相携えて、まず東洋の平和を確立」この言葉から番組は始まります。
昭和初期、日本は不況に苦しんでいました。その状況を打破したのは、皮肉にも戦争がもたらした経済復興でした。満州国建国により軍需産業と輸出が拡大し、失業率も改善。国民は「戦争がもたらす好景気」を実感し、中国との戦争を歓迎、さらにアメリカとの戦争を望む空気すら生まれていきます。
満州事変と宰相たち
1931年9月18日、奉天(現在の瀋陽)郊外で南満州鉄道の線路が爆破されました(柳条湖事件)。これをきっかけに関東軍は独断で軍事行動を展開し、満州全土を占領。最終的に傀儡国家「満洲国」を樹立します。番組では、この爆破が関東軍の自作自演であったことを認めています。
当時の第28代首相・若槻禮次郎は、政府方針に反する軍の独断行動を追認せざるを得ませんでした。満州国を宣伝する映画では、こう語られます。「満蒙の天地はまさに我々日本人によって開発されねばなりません。このまま推移すれば、日本国民はただ座して死を待つのみです。総額130万平方キロの豊かな資源に恵まれた満蒙を開拓することによってこそ、日本は国防的にも経済的にも存立しうるのです。」
大阪朝日新聞は、爆弾事故で亡くなった3名の軍人を「軍神・肉弾三勇士」と讃え、虚偽の記事を国民に広めました。映画や歌まで制作され、国民の戦意は高揚していきました。
犬養毅と軍部台頭
満州国に反対した第29代首相・犬養毅は1931年12月に就任しましたが、1932年5月15日、五・一五事件で暗殺されます。後を継いだ第30代首相・斎藤實(海軍大将)のもとで政党内閣は終焉を迎えました。
1936年の二・二六事件では、陸軍青年将校らが政府要人を襲撃し、永田町・霞が関一帯を占拠。軍を批判した東京朝日新聞も標的となり、新聞は軍を自由に批判できなくなりました。しかし昭和天皇の強い怒りによって鎮圧され、青年将校たちは投降、あるいは自決して事件は収束します。この結果、岡田内閣が総辞職し、後継の広田内閣は思想犯保護観察法を成立させました。
近衛文麿の登場
首相推薦の重責を担った元老・西園寺公望は、軍の暴走を抑えるため近衛文麿を首相に選びます。第1次近衛内閣では、盧溝橋事件をきっかけに日中戦争が勃発。近衛は不拡大方針を掲げましたが軍の強硬論に押され、「北支派兵声明」「近衛声明」「東亜新秩序」などを打ち出し、国家総動員法を施行して戦時体制を強化しました。
その後も新体制運動を唱え大政翼賛会を設立し、国内の全体主義化を推進。外交面では「八紘一宇」「大東亜共栄圏」を掲げ、日独伊三国同盟や日ソ中立条約を締結しました。戦後は東久邇宮内閣の国務大臣として憲法改正に意欲を見せましたが、A級戦犯に指定され、服毒自決しました。
戦争と国民
戦時下の新聞は連日勇ましい記事で国民を煽り、批判はほとんど不可能でした。近衛文麿は外交で対米戦争を避けようと努力しましたが挫折。後継の東条英機も交渉を続けましたが、国民世論の熱狂を抑えきれず、最終的に開戦を決断します。
南京陥落後、国民は領土拡大や賠償金に大きな期待を抱きました。ちなみに、日清戦争後の下関条約で清国から得た賠償金(計2億3,150万両、庫平銀)は、当時の日本GDPの約4割に相当しました。この成功体験が、国民にさらなる戦果を期待させていきます。
戦争が長引くにつれ、中国を支援する英米との対立が深まり、日本はドイツ・イタリアと軍事同盟を結び、やがて世界規模の戦争へ突入していきました。
映像を通じて、私たちは「なぜ日本が第二次世界大戦に参加していったのか」、その歴史的背景の一端を理解できます。歴史を知らない若い世代こそ、この番組を見るべきだと思います。

2025-09-02