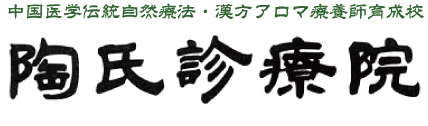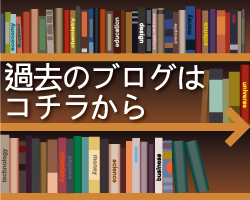2025-12-18
100回施療記念(好酸球性多発血管炎性肉芽腫症)
2025-12-17
中年女性にとっての朗報(老化?)
2025-12-16
生命とエネルギー
2025-12-15
次元と共鳴
2025-12-14
我が家とFFCパイロゲン
2025-12-13
地震と準備
2025-12-12
命と気持ち(骨軟部腫瘍(肉腫))
2025-12-11
中国医学と哲学②
2025-12-10
中国医学と哲学①
2025-12-09
病気と元気 ― 同じ「気」から生まれるもの
2025-12-08
開拓と継承
2025-12-07
第12回 北海道中国会 総会&懇親会
2025-12-06
ノーベル生理・医学賞に輝いた中国医学理論の魅力
2025-12-05
戦略と戦術の観点で見る中国医学と西洋医学
2025-12-04
Let’s enjoy cooking!
過去ブログはこちらから
4
食と行動
新年号の科学雑誌「The Scientist」に、スネハ・ケドカル氏の研究論文「なぜ人によって食習慣が違うのでしょうか?」が掲載されていました。
人々の食事内容や食べる量は千差万別です。その多様性の背後には、腸内細菌叢が一つの重要な要因として関与している可能性があります。ルーヴァン・カトリック大学で腸内細菌叢が食物報酬行動に及ぼす影響を研究している生理学者アマンディーヌ・エヴァラード氏は、「腸内細菌が食事を制御するという考えは非常に理にかなっています」と述べています。この研究は主に動物を対象に進められています。
研究者たちは、腸内細菌が宿主の摂食習慣にどのような影響を与えるかを解明するために、様々な動物モデルを使用しています。たとえば、線虫(Caenorhabditis elegans)の餌探し行動に細菌がどのような役割を果たすかを調査した結果、線虫に自然に存在する細菌が神経伝達物質を生成し、それが嗅覚ニューロンに作用して線虫の摂食習慣を調節することが明らかになりました。同様に、キイロショウジョウバエの食習慣についての研究では、腸内細菌が生成する乳酸が宿主の摂食決定を変えることが分かりました。
哺乳類を対象とした報告では、腸内細菌叢が宿主の感覚や摂食行動を調節する同様の効果が示唆されています。マウスに抗生物質を投与して腸内細菌叢を枯渇させた実験では、食習慣の変化が観察され、一部の嗜好性の高い食品を過剰に摂取するようになりました。ピッツバーグ大学で腸内微生物叢と宿主の相互作用を研究している生態学者ケビン・コール氏は、「抗生物質の研究から多くのことを学んできましたが、同時に抗生物質が動物に他の多くの変化を引き起こすことも分かっています」と指摘しています。
エヴァラード氏は、マウスの実験で腸内細菌が食物の嗜好に影響を与える証拠があるものの、「人間においてこの因果関係を証明するのは非常に難しい」と述べています。実際、人間を対象とした腸内細菌叢と食物嗜好に関する研究報告では、両者の間に相関関係は見られるものの、因果関係の証明には至っていないとされています。
**人間における「食と行動」**に関する研究では、動物実験で見られるような関連性がまだ十分に証明されていないものの、その可能性には注目する価値があります。
環境、民族性、習慣、遺伝といった要因が食習慣と行動に及ぼす影響を解明することで、健康維持や病気の治療に大きく貢献できるでしょう。ただし、真実に迫るためには、さらに創意工夫を凝らした研究視点や方法が求められます。
人々の食事内容や食べる量は千差万別です。その多様性の背後には、腸内細菌叢が一つの重要な要因として関与している可能性があります。ルーヴァン・カトリック大学で腸内細菌叢が食物報酬行動に及ぼす影響を研究している生理学者アマンディーヌ・エヴァラード氏は、「腸内細菌が食事を制御するという考えは非常に理にかなっています」と述べています。この研究は主に動物を対象に進められています。
研究者たちは、腸内細菌が宿主の摂食習慣にどのような影響を与えるかを解明するために、様々な動物モデルを使用しています。たとえば、線虫(Caenorhabditis elegans)の餌探し行動に細菌がどのような役割を果たすかを調査した結果、線虫に自然に存在する細菌が神経伝達物質を生成し、それが嗅覚ニューロンに作用して線虫の摂食習慣を調節することが明らかになりました。同様に、キイロショウジョウバエの食習慣についての研究では、腸内細菌が生成する乳酸が宿主の摂食決定を変えることが分かりました。
哺乳類を対象とした報告では、腸内細菌叢が宿主の感覚や摂食行動を調節する同様の効果が示唆されています。マウスに抗生物質を投与して腸内細菌叢を枯渇させた実験では、食習慣の変化が観察され、一部の嗜好性の高い食品を過剰に摂取するようになりました。ピッツバーグ大学で腸内微生物叢と宿主の相互作用を研究している生態学者ケビン・コール氏は、「抗生物質の研究から多くのことを学んできましたが、同時に抗生物質が動物に他の多くの変化を引き起こすことも分かっています」と指摘しています。
エヴァラード氏は、マウスの実験で腸内細菌が食物の嗜好に影響を与える証拠があるものの、「人間においてこの因果関係を証明するのは非常に難しい」と述べています。実際、人間を対象とした腸内細菌叢と食物嗜好に関する研究報告では、両者の間に相関関係は見られるものの、因果関係の証明には至っていないとされています。
**人間における「食と行動」**に関する研究では、動物実験で見られるような関連性がまだ十分に証明されていないものの、その可能性には注目する価値があります。
環境、民族性、習慣、遺伝といった要因が食習慣と行動に及ぼす影響を解明することで、健康維持や病気の治療に大きく貢献できるでしょう。ただし、真実に迫るためには、さらに創意工夫を凝らした研究視点や方法が求められます。

2025-01-12