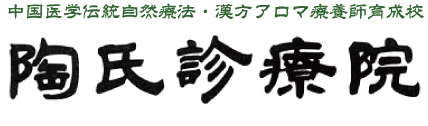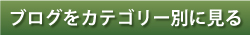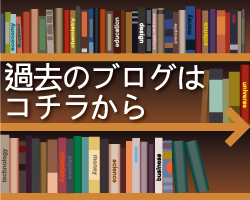▼陶氏療法バックナンバー
2025-12-02
量子療法の威力骨軟部腫瘍(肉腫)
2025-11-26
植物の入退院
2025-11-11
健康意識の若年化(胃腸弱い)
2025-10-29
陶氏療法中の量子療法技術 その一:刮痧(カッサ)
2025-10-24
朗報:乳がん消失
2025-10-21
医療の目的
2025-10-12
施療後の感想にみる生命の調律― 未病学エッセイ ―「子宮筋腫」,「不整脈」,「糖尿病」
2025-10-02
DENBAマットの実験
2025-09-28
耳石症
2025-09-26
病気の原因
2025-09-24
入浴剤の発汗作用と寒気への対応(風邪予防&治療)
2025-09-14
食事療法の主役~自宅で作る発芽発酵玄米ごはん~
2025-09-12
患者さんの要望
2025-08-27
生命力と治療効果(左耳下腺腫瘍)
2025-07-26
89歳夫婦が営む名物だんご店
過去ブログはこちらから
医療の目的
カテゴリー 陶氏療法
現代医療では、あらゆる治療にガイドラインが設けられています。そのため、ガイドラインに同意しない患者には、必要な医療行為であっても提供されないことがしばしば見られます。
最近、札幌在住の50代の胆管がん患者さんが来院されました。
二年前、健康診断で胆管の異常を指摘され、精査の結果「胆管がん」と診断されました。病院からは抗がん剤治療や手術を勧められましたが、ご本人はそれを拒否し、自らの力で一年間頑張ってこられました。
昨年6月から当診療院に通い始め、10か月間の施療で体調が改善し、仕事にも復帰できるようになりました。
しかし、5か月ほど施療を休んだ後、腹痛・発熱・黄疸が出現し、再び施療を再開しました。施療により腹痛は緩和し、黄疸も軽減しましたが、ときどき高熱が出て全身の不調が続き、食欲も減退していきました。
それでも患者さんは2年間、強い意志で病と向き合ってきました。
ところが、病院側は抗がん剤や手術を拒否したことを理由に、主治医から「緩和ケア病院」への転院を勧められました。本人はそれも望まず、自宅療養を続けています。
現在は食事がほとんど摂れず、衰弱が進んでいます。それにもかかわらず、病院では「末期がんによる低タンパク血症と貧血」のため、輸血などの治療を行わない方針でした。私たちはただ、少しでも食事を摂るよう励ますしかありません。
確かに、終末期医療では治療の目的が「延命」から「QOL(生活の質)の維持・向上」へと移行することは理解できます。
しかし、本人がまだ諦めておらず、「救命的な医療」も受けたいという意志を持っている場合、それを拒むことには疑問を感じます。
一方で、地方に住む70代の男性耳下腺がんの患者さんは、抗がん剤治療を受けながら、摂食困難と貧血を起こしましたが、地元の病院ではすぐに入院し、輸血治療が行われました。
同じ「末期がん」であっても、医師や病院によって対応が大きく異なる現実があります。これは、現代医療が抱える大きな課題の一つではないでしょうか。
医療は「患者中心」であるべきか、それとも「医療機関中心」で進められているのか。医療従事者として、まずこの根本的な問いを見つめ直す必要があります。
終末期がん患者への治療方針は、もはや根治を目指すものではなく、苦痛を和らげ、より良い最期を迎えることに重きを置きます。
しかし、貧血に対する輸血のような処置も、単なる延命目的ではなく、患者本人の意思を尊重し、QOLを少しでも高めるために行うという視点が必要です。その判断が「慎重すぎる」現実に、現代医療の限界と課題が見えてきます。
最近、札幌在住の50代の胆管がん患者さんが来院されました。
二年前、健康診断で胆管の異常を指摘され、精査の結果「胆管がん」と診断されました。病院からは抗がん剤治療や手術を勧められましたが、ご本人はそれを拒否し、自らの力で一年間頑張ってこられました。
昨年6月から当診療院に通い始め、10か月間の施療で体調が改善し、仕事にも復帰できるようになりました。
しかし、5か月ほど施療を休んだ後、腹痛・発熱・黄疸が出現し、再び施療を再開しました。施療により腹痛は緩和し、黄疸も軽減しましたが、ときどき高熱が出て全身の不調が続き、食欲も減退していきました。
それでも患者さんは2年間、強い意志で病と向き合ってきました。
ところが、病院側は抗がん剤や手術を拒否したことを理由に、主治医から「緩和ケア病院」への転院を勧められました。本人はそれも望まず、自宅療養を続けています。
現在は食事がほとんど摂れず、衰弱が進んでいます。それにもかかわらず、病院では「末期がんによる低タンパク血症と貧血」のため、輸血などの治療を行わない方針でした。私たちはただ、少しでも食事を摂るよう励ますしかありません。
確かに、終末期医療では治療の目的が「延命」から「QOL(生活の質)の維持・向上」へと移行することは理解できます。
しかし、本人がまだ諦めておらず、「救命的な医療」も受けたいという意志を持っている場合、それを拒むことには疑問を感じます。
一方で、地方に住む70代の男性耳下腺がんの患者さんは、抗がん剤治療を受けながら、摂食困難と貧血を起こしましたが、地元の病院ではすぐに入院し、輸血治療が行われました。
同じ「末期がん」であっても、医師や病院によって対応が大きく異なる現実があります。これは、現代医療が抱える大きな課題の一つではないでしょうか。
医療は「患者中心」であるべきか、それとも「医療機関中心」で進められているのか。医療従事者として、まずこの根本的な問いを見つめ直す必要があります。
終末期がん患者への治療方針は、もはや根治を目指すものではなく、苦痛を和らげ、より良い最期を迎えることに重きを置きます。
しかし、貧血に対する輸血のような処置も、単なる延命目的ではなく、患者本人の意思を尊重し、QOLを少しでも高めるために行うという視点が必要です。その判断が「慎重すぎる」現実に、現代医療の限界と課題が見えてきます。

2025-10-21