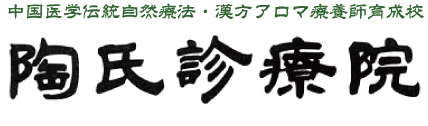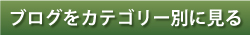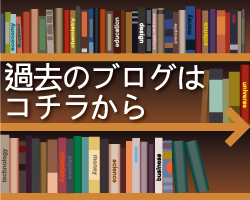▼その他バックナンバー
2026-01-07
北海道の除雪の楽しみ
2025-12-08
開拓と継承
2025-12-07
第12回 北海道中国会 総会&懇親会
2025-11-03
中国の有人宇宙船「神舟21号」11月1日に打ち上げ成功
2025-11-01
東西文化の相違と社会形成
2025-10-20
理想の人生の模範
2025-10-15
故郷への愛
2025-10-14
黄金の秋・収穫の10月
2025-10-08
観光ラッシュ
2025-10-07
北海道観光機構への表敬訪問
2025-10-06
自転車譲渡事業の継続
2025-10-03
中国の定年後の生活
2025-10-01
連休と経済
2025-09-27
中華人民共和国成立七十六周年祝賀レセプション
2025-09-11
診療院の自然環境
過去ブログはこちらから
漢字と脳とAI①
カテゴリー その他
今年、中国のAI企業「DeepSeek」が発表した新技術は、その低コストかつ低エネルギー消費の特性により、AI業界に大きな波紋を広げました。その根本的な理由は、漢字の特性と人間の脳の神経回路の仕組みが密接に関連していることにあります。
李柯商業顧問のショート動画の話を説明して、参考になります。
まず、3500年の歴史を持つ漢字の成り立ちについて説明します。
漢字の造字法:「六書」
漢字には六種類の作り方(造字)があり、「六書(りくしょ)」と呼ばれます。それぞれ、象形(しょうけい)、指事(しじ)、会意(かいい)、形声(けいせい)、転注(てんちゅう)、仮借(かしゃ)です。
象形:物の形をかたどり、視覚的に意味を表す方法です。例えば、「日」は太陽、「月」は月の形を描いたものです。最も原始的な造字法といえます。
指事:記号や符号を用いて、抽象的な概念を表します。例えば、「上」と「下」は横線の上下に短い線を加えることで、それぞれの位置関係を示します。「本」は「木」の根元に線を加えることで「根本」の意味を表しています。
会意:意味を持つ二つ以上の漢字を組み合わせ、新たな意味を作ります。例えば、「休」は「人」と「木」から成り、「人が木にもたれかかって休む」ことを表します。「明」は「日」と「月」の組み合わせで「明るさ」を示します。
形声:意味を示す部分(形符)と発音を示す部分(声符)で構成される漢字です。例えば、「河」は「氵(水)」が形符で水に関連し、「可」が声符として発音を示します。「材」は「木」が形符、「才」が声符になっています。
転注:ある漢字が、元の意味から派生して別の意味を持つようになる造字法です。例えば、「考」と「老」は、古代において「考」には「年老いる」という意味があり、「老」と近い意味を持っていたため、相互に解釈されるようになりました。
仮借:発音が似ているが、適切な文字が存在しない場合に、別の漢字を借りて使用する方法です。例えば、「自」は本来「鼻」の象形文字でしたが、「自己」という意味で借用されました。「而」はもともと「ひげ」を表していましたが、接続詞「そして」「しかも」として使われるようになりました。
漢字と脳の情報処理
漢字はその造字法により、単なる表音文字とは異なり、多層的な情報を内包しています。文字の構造そのものが意味を持つため、視覚的・概念的な記憶を強く刺激し、空間的な認知を促します。これにより、漢字の情報処理は、アルファベットなどの表音文字に比べて高い効率を誇ります。
実際に、国際連合(国連)の公式資料を比較すると、中国語の文書は同じ内容の英語文書に比べて約30%薄いことが分かっています。これは、漢字が少ない文字数でより多くの情報を伝達できることを示しています。
漢字を認識する際の脳の神経回路は、空間的なパターン認識を重視する傾向があり、情報の圧縮率が高いため、学習効率の向上やエネルギー消費の削減につながる可能性があります。この特性は、AIの認識モデルにも応用できると考えられています。
このように、漢字は単なる文字ではなく、脳の情報処理と深く関わる高度なシステムであり、AIの発展においても新たな可能性をもたらしています。
李柯商業顧問のショート動画の話を説明して、参考になります。
まず、3500年の歴史を持つ漢字の成り立ちについて説明します。
漢字の造字法:「六書」
漢字には六種類の作り方(造字)があり、「六書(りくしょ)」と呼ばれます。それぞれ、象形(しょうけい)、指事(しじ)、会意(かいい)、形声(けいせい)、転注(てんちゅう)、仮借(かしゃ)です。
象形:物の形をかたどり、視覚的に意味を表す方法です。例えば、「日」は太陽、「月」は月の形を描いたものです。最も原始的な造字法といえます。
指事:記号や符号を用いて、抽象的な概念を表します。例えば、「上」と「下」は横線の上下に短い線を加えることで、それぞれの位置関係を示します。「本」は「木」の根元に線を加えることで「根本」の意味を表しています。
会意:意味を持つ二つ以上の漢字を組み合わせ、新たな意味を作ります。例えば、「休」は「人」と「木」から成り、「人が木にもたれかかって休む」ことを表します。「明」は「日」と「月」の組み合わせで「明るさ」を示します。
形声:意味を示す部分(形符)と発音を示す部分(声符)で構成される漢字です。例えば、「河」は「氵(水)」が形符で水に関連し、「可」が声符として発音を示します。「材」は「木」が形符、「才」が声符になっています。
転注:ある漢字が、元の意味から派生して別の意味を持つようになる造字法です。例えば、「考」と「老」は、古代において「考」には「年老いる」という意味があり、「老」と近い意味を持っていたため、相互に解釈されるようになりました。
仮借:発音が似ているが、適切な文字が存在しない場合に、別の漢字を借りて使用する方法です。例えば、「自」は本来「鼻」の象形文字でしたが、「自己」という意味で借用されました。「而」はもともと「ひげ」を表していましたが、接続詞「そして」「しかも」として使われるようになりました。
漢字と脳の情報処理
漢字はその造字法により、単なる表音文字とは異なり、多層的な情報を内包しています。文字の構造そのものが意味を持つため、視覚的・概念的な記憶を強く刺激し、空間的な認知を促します。これにより、漢字の情報処理は、アルファベットなどの表音文字に比べて高い効率を誇ります。
実際に、国際連合(国連)の公式資料を比較すると、中国語の文書は同じ内容の英語文書に比べて約30%薄いことが分かっています。これは、漢字が少ない文字数でより多くの情報を伝達できることを示しています。
漢字を認識する際の脳の神経回路は、空間的なパターン認識を重視する傾向があり、情報の圧縮率が高いため、学習効率の向上やエネルギー消費の削減につながる可能性があります。この特性は、AIの認識モデルにも応用できると考えられています。
このように、漢字は単なる文字ではなく、脳の情報処理と深く関わる高度なシステムであり、AIの発展においても新たな可能性をもたらしています。

2025-03-01